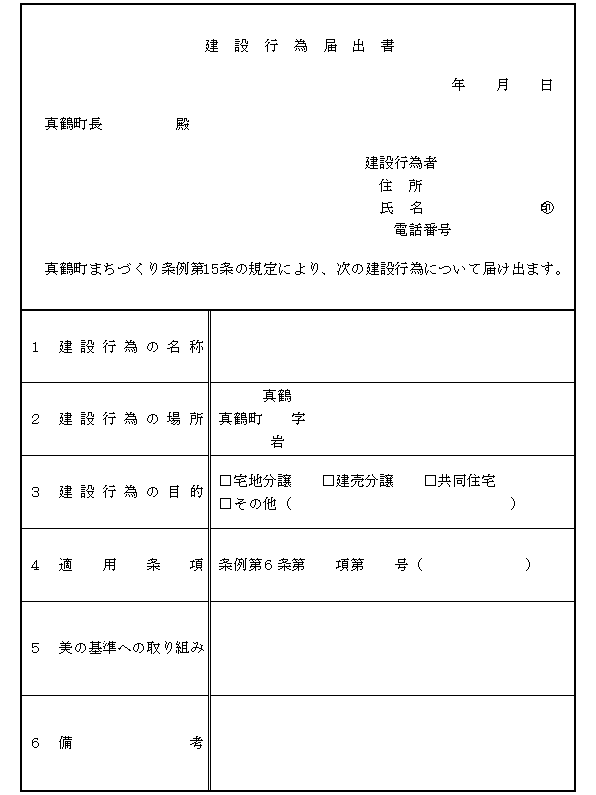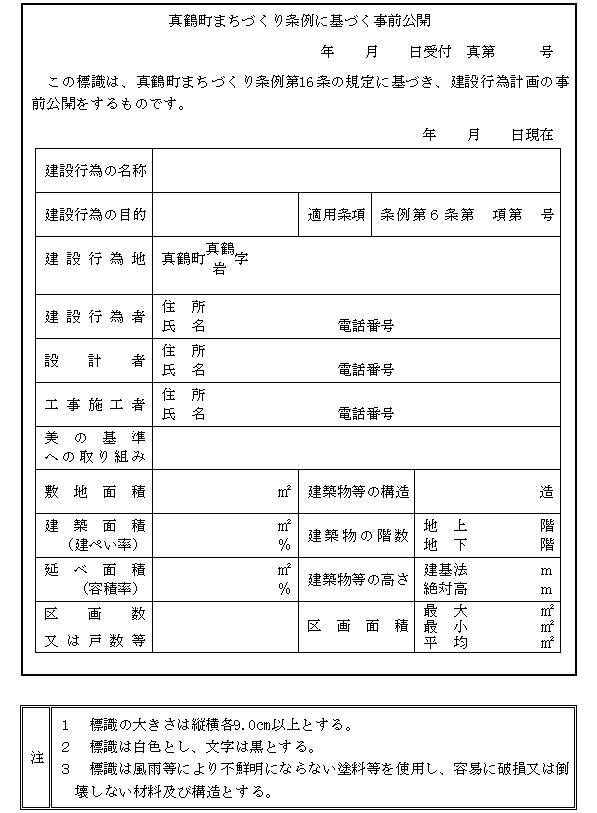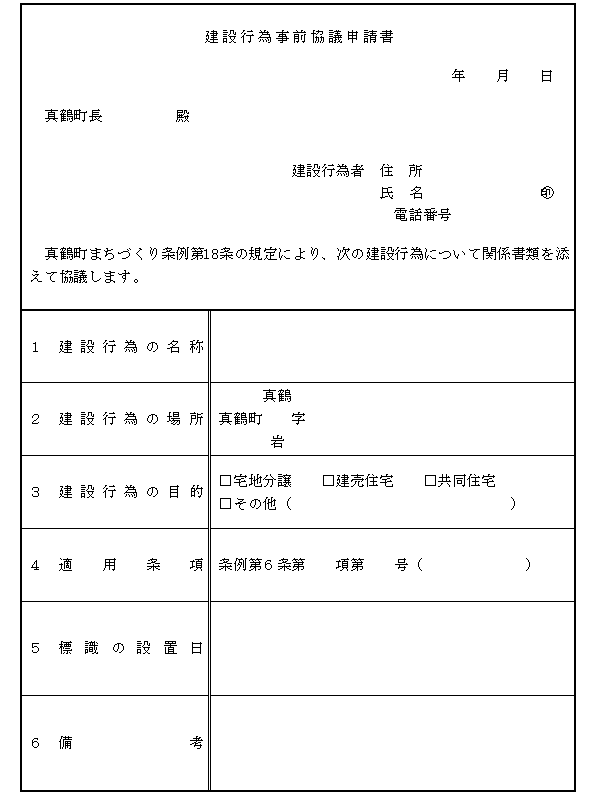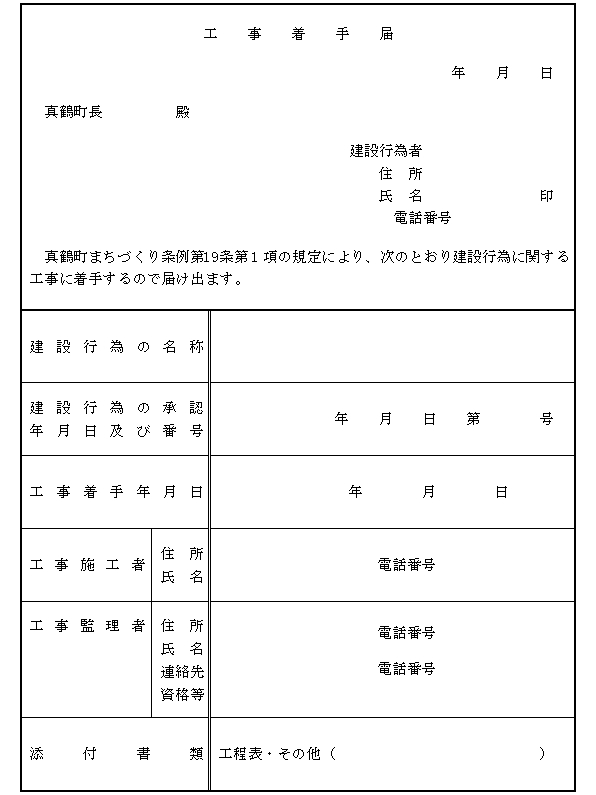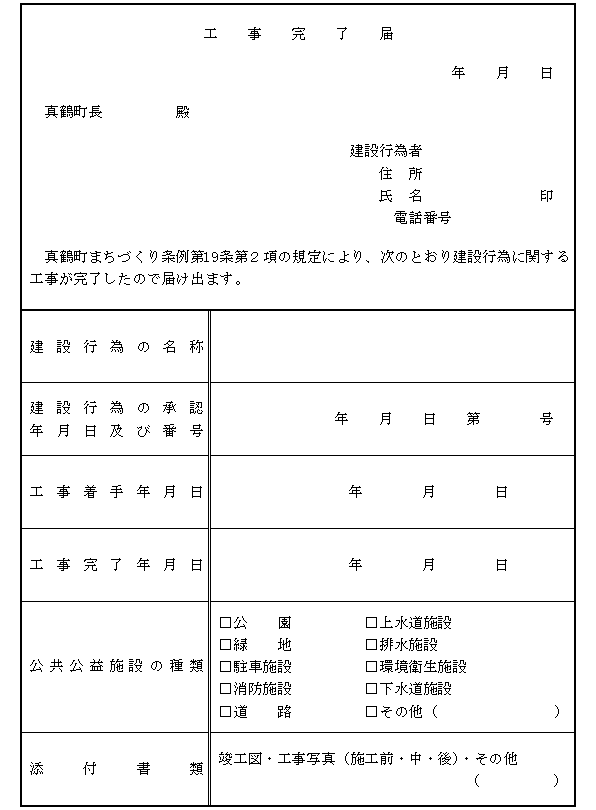○真鶴町まちづくり条例施行規則
平成5年10月6日規則第10号
真鶴町まちづくり条例施行規則
(趣旨)
(近隣関係者)
(土地利用規制規準)
2 前項の規定にかかわらず、
条例施行の際現に存在している建築物で、建築物の用途の制限に適合しないものについては、建築物の用途の制限を除く土地利用規制規準の範囲内で行われる当該建築物の延べ面積の1.2倍の範囲内で行われる同一用途の増築又は改築については、建築物の用途の制限は適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、
条例施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で土地利用規制規準の敷地面積の最小限度の面積に満たないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するもの及び町長が特に認めたものならば、土地利用規制規準の敷地面積の最小限度の面積に満たない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては土地利用規制規準の敷地面積の最小限度の制限は適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、用途地域の定めのない区域において土地利用規制規準の用途の制限に適合しない建築が計画されたとき、一定の基準を満たす場合において、まちづくり審議会の意見を聴取して町長が認めた場合のみ建築を行うことができるものとする。
(保全区域)
(1) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)に基づいて自然環境保全地域に指定された区域
(2) 神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号。以下「自然公園条例」という。)に基づいて第一種特別地域に指定された区域
(誘導区域)
(1) 自然公園条例に基づいて第三種特別地域に指定された区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に規定する地区計画等の策定が予定されている区域
(美の基準)
第6条 条例第10条に規定する美の基準は、別に定めるデザインコードによるものとする。
(公園及び緑地)
第7条 条例第12条第1項第1号に規定する公園は、建設行為における建設区域面積が3,000平方メートル以上の場合は、その面積の100分の3以上の公園を別に定める基準により設置するものとする。ただし、建設行為の用途又は周辺の状況等により特に必要がないと町長が認めたときは、この限りでない。
2 建設行為者は、建設行為における建設区域面積が1,000平方メートル以上の場合は、斜面山林等の既存樹木を極力保存しながら、別に定める基準により緑地を確保するものとし、1,000平方メートル未満の場合にあっては、町長と協議するものとする。
(駐車施設)
第8条 条例第12条第1項第2号に規定する駐車施設は、建設行為における建設区域面積が、1,000平方メートル以上の場合は、次の各号の基準により原則として建設区域内に設置するものとする。
(1) 宅地の区画分譲等建設行為については、全宅地区画数
(2) 共同住宅建設行為については、住宅戸数の3分の2以上の数
(3) その他の建設行為については、町と協議し決定する数
2 駐車施設は、前項により整備する台数分の、縦5メートル、横2.5メートルの長方形を標準とする区画及び駐車に必要な通路を配置するものとする。
(消防施設)
第9条 条例第12条第1項第3号に規定する消防施設は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)(以下「消防水利の基準」という。)第2条に規定する消防水利及び第4項に規定する空地とする。
2 消防水利は、防火水槽を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める消防水利に代えることができる。
(1) 2以上の消防水利を設置するときの一部の消防水利 消火栓又は将来とも継続して設置されることが確実な他の消防水利
(2) 宅地分譲又は建売分譲を目的とし、及び当該建設区域内の防火対象物から既設防火水槽に至る距離が消防水利の基準第4条に規定する基準を満たしている区画数10未満の開発行為 消火栓
3 前項第2号の場合において、同号の規定の適用を受けた後に区画を分割したとき又は同一建設行為者が施工中若しくは施工後3年以内に当該建設区域に接続して更に建設行為を行うとき(以下「同一建設行為」という。)の区画数は、それぞれ分割後の数又は当該建設行為による数及び同一建設行為による数の合計の数により算定するものとする。
4 建設行為者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、既設消防水利により消防活動上支障がないと町長が認めたときは、消防水利を設置しないことができる。
(1) 共同住宅(長屋を含む。)で、その戸数が20未満の建築物の建設行為
(2) 建設区域面積が、1,000平方メートル未満の建設行為
(3) 主として建築物の建築の用に供する目的で行われない建設行為
5 建設行為者は、建築物等周辺に消防活動に必要な空地を確保するものとする。
6 消防施設の設置に関するその他必要な事項については、別に定める基準による。
(道路)
2 建設区域内に設置する道路は、建設区域外にある既存道路の機能を阻害せず、及びこれらの道路と一体となって機能が有効に発揮されるよう計画しなければならない。
3 建設行為者は、前項の道路に次の各号のいずれかに該当する箇所があるときは、当該箇所に防護施設及び交通安全施設を設置しなければならない。
(1) がけ面又は河川に接している箇所
(2) 屈曲している箇所
(3) 歩行者、通行車両及び町民等の安全確保に必要な箇所
4 建設行為者は、道路の路面に、電柱等の交通障害となるような施設を設置しないものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合にはこの限りではない。
5 道路及び付属施設に関する構造その他の基準については、別に定めるもののほか道路法その他関係法令の基準に準じて計画しなければならない。
(上水道施設)
第11条 条例第12条第1項第5号に規定する上水道施設を整備する場合において、建設行為者は、当該建設区域の給水計画について町長と協議しなければならない。
2 建設行為者は、建設区域内の上水道の設計、施工について、町の定める基準及び仕様書に基づき、町長の承認を得て自らの費用で施工し、完成後は上水道施設の全部(止水栓以下の給水装置を除く。)を無償譲渡するものとする。
3 給水施設設置の基準については、別に定めるところによる。
(排水施設)
第12条 条例第12条第1項第6号に規定する排水施設は、建設行為の規模、地形及び用途を勘案して、汚水及び雨水を有効に排除できる規模、構造を有するものとする。ただし、海又はその他の水利に直接放流する場合は、あらかじめその管理者又は権利者と協議しなければならない。
2 排除方式は、汚水と雨水を別々の管渠で排除する分流式とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
3 汚水処理は、次によるものとする。
(1) 公共下水道計画区域内の処理開始区域 公共下水道管渠接続処理
(2) 前号以外の区域 し尿及び雑排水等を処理できる施設(以下「処理施設」という。)の設置による処理
4 前項第2号の区域で、公共下水道が処理開始された場合においては、遅滞なく公共下水道計画に基づき切替え処理するものとする。
5 処理施設は、建設行為者又は利用者若しくはその利用者団体で管理運営するものとする。
6 建設行為者は、建設区域外の排水可能な地点まで排水施設を整備するものとする。ただし、既設の排水施設に接続する場合で、周辺地域に溢水等の恐れが生ずるときは、建設行為者は、当該既設排水施設を町長が指示する区間まで整備するものとする。
7 建設行為者は、前項の施設で町が必要と認めるものについては、町に無償譲渡するものとする。
8 建設行為者は、排水施設の改良整備が長期又は困難な事情にある場合及び建設行為の規模、地形等の状況により、必要に応じて一時雨水を貯留する施設を設置するものとする。
9 排水施設に関するその他の基準については、別に定めるところによる。
(環境衛生施設)
2 ごみ集積場所は、建設区域内のごみ収集の円滑を図るため、町のごみ収集作業に適した場所に設置するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 建設行為の位置又は規模等により町長が必要と認める場合は、指示された場所に建設行為者が自らごみを搬入し、又は処理するものとする。
4 環境衛生施設に関するその他の基準については、別に定めるところによる。
(その他の公共公益施設)
第14条 条例第12条第1項第8号に規定するその他の公共公益施設は、町長が必要と認める施設について協議の上、整備するものとする。
(公共公益施設整備の負担等)
第15条 条例第12条第1項各号に規定する公共公益施設の整備に必要な用地及び費用は、建設行為者が負担するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(建設行為届出書)
2 届出に必要な関係書類は、
別表第3に掲げるもののうち町長が指示する書類とする。
(事前公開の標識)
(事前協議申請書)
2 申請に必要な関係書類は、
別表第4に掲げるもののうち町長が指示する書類とする。
(工事着手届出及び工事完了届)
(報告書の作成)
第20条 条例第23条に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 建設行為計画案の概要
(2) 公聴会の開催日時及び場所
(3) 公述人の住所、氏名及び年齢
(4) 公述人及び建設行為者の述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(6) 公聴会の議長の意見等
(7) 当該建設行為計画案に係る町長の当否の意見
(緑地保全の貢献)
第21条 条例第30条に規定する協力は、真鶴町みどり基金への、建設区域面積1平方メートルあたり500円を乗じて得た額の寄附とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
条例の公布の日前から、真鶴町土地利用指導基準(平成2年告示第33号)により、その土地利用について、指導を行ってきた建設行為であって、
条例施行の日の前日までに、真鶴町宅地開発等指導要綱(平成元年告示第13号)第4条の規定による協定を締結し、かつ、当該協定を締結した日から起算して1年以内に着手される建設行為については、
条例第6条の規定は適用しない。
附 則(平成6年8月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年5月10日規則第6号)
この規則は、平成8年5月10日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第8号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
近隣関係者の範囲
建設行為の区分 | 近隣関係者の範囲 |
条例第6条第2項第1号の規定による行為 | 建設区域が1,000㎡未満のもの | 建設行為予定敷地内の隣地境界線から6m以内の土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
建設区域が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの | 建設行為予定敷地内の隣地境界線から8m以内の土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
建設区域が3,000㎡以上のもの | 建設行為予定敷地内の隣地境界線から16m以内の土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
条例第6条第2項第2号の規定による行為 | 建設行為予定敷地内の隣地境界線から4m以内の土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
条例第6条第2項第3号ア、イ及びウの規定による行為 | 建設行為予定敷地内の隣地境界線から建築物等の最低部分より最高部分までの高さと同じ距離の範囲内に存する土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
条例第6条第2項第3号エの規定による行為 | 町と協議した範囲に存する土地又は建築物等の所有者及び占有者 |
別表第2(第3条関係)
土地利用規制規準
地区区分 | 土地利用の方針 | 建ぺい率 容積率 | 建築物の用途の制限 | 高さの最高限度 | 敷地面積の最小限度 | 壁面の後退 |
道路境界 |
臨海地区 | 真鶴町の観光と産業を発展させるための核として、臨海地区としての特徴を活かした土地利用と再開発を誘導する。 | 60% | 準工業地域内で禁止されている建築物及び150㎡を超える工場は建築できない。 | 15m | 100㎡ | ― |
200% | | | |
商業地区 | 真鶴半島及び真鶴港の玄関として又導入路として魅力とにぎわいのある商業地区として整備・誘導する。 | 80% | 近隣商業地域内で禁止されている建築物は建築できない。 | 12m | 100㎡ | ― |
200% | | | |
普通住宅地区 | 既存の住宅地として用途の混在を認めながら環境の保全と修復を進める。 | 60% | 第一種住居地域内で禁止されている建築物、500㎡を超える店舗、事務所、ホテル又は旅館等は建築できない。 (ただし、都市計画法に基づき第一種中高層住居専用地域に指定されている地域では、建築基準法別表第2(は)項で建築できるもの以外の建築物は建築できない。) | 甲地区 | 120㎡ | ― |
200% | 12m | 集合住宅については1戸あたり30㎡を加算した面積 | |
| | 乙地区 | 150㎡ | 1m |
| | 10m | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 | |
| | 屋根は傾斜屋根とする。 | |
専用住宅地区 | 新しい良好な住宅地として居住環境の保全を図る。 | 60% | 立ケ窪・風越地区地区計画(平成8年真鶴町告示第9号)の地区整備計画による。 |
200% |
住工協調地区 | 住宅と工業が混在した地区で、今後、住宅と工業が協調して混在できるよう整備・誘導を図る。 | 60% | 準工業地域及び第二種住居地域内で禁止されている建築物で工場を除いた建築物は建築できない。 | 12m | 120㎡ | 住宅については1m 工場については1.5mかつ、1m後退した位置に生け垣を設け道路との間には植栽する。生け垣の高さは、道路面より1.5mとする。 |
200% | ただし、工作物はこの限りではない。 | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 |
工業地区 | 採石場及び石材産業振興に寄与する工業地区として育成する。 | 60% | 工業地域内で禁止されている建築物は建築できない。 (ただし、建築基準法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる工場及び第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するものは建築できない。) | 12m | 120㎡ | 1.5mかつ、1m後退した位置に生け垣を設け道路との間には植栽する。 生け垣の高さは、道路面より1.5mとする。 |
200% | ただし、工作物はこの限りではない。 | |
緑住地区 | 自然環境及び景観と調和した良好で低層の住宅地として漸次整備・誘導を図る。 | 50% | 第一種中高層住居専用地域内で禁止されている建築物は建築できない。ただし、ホテル、旅館等はこの限りではない。 | 12m | 150㎡ | 1m |
100% | 屋根は傾斜屋根とする。 | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 | |
景観普通地区 | 優れた自然環境と景観を保全するため開発は抑制する。ただし、町の観光、工業及び農業の発展に寄与し、自然環境と景観、特に海の眺望と斜面緑地の保全を図るものについては許容する。 | 50% | 第一種低層住居専用地域内で建築できるもののほか、以下に掲げる建築物は建築できる。①店舗、飲食店 ②ホテル、旅館 ③石材採取、加工に要する施設 | 10m | 150㎡ | 1m |
100% | 屋根は傾斜屋根とする。 | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 | |
半島景観特別地区 | 真鶴半島の優れた自然環境と景観の保全を図るため開発は抑制する。ただし、半島の自然環境と景観を活かし、眺望と緑地と調和したものについては許容する。 | 50% | 第一種低層住居専用地域内で建築できるもののほか、以下に掲げる建築物で、環境、景観上特に認められるものは建築できる。①店舗、飲食店 ②ホテル、旅館 | 10m | 150㎡ | 1m |
100% | 屋根は傾斜屋根とする。 | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 | |
沿岸景観特別地区 | 海岸に沿った沿岸地域の優れた斜面緑地と景観の保全を図る。 | 50% | 第一種低層住居専用地域内で建築できるもののほか店舗、飲食店で環境、景観上特に認められたものは建築できる。 | 10m | 150㎡ | 1m |
100% | 屋根は傾斜屋根とする。 | 集合住宅については1戸あたり40㎡を加算した面積 | |
自然環境地区 | 真鶴町の貴重な自然環境を将来に継承できるよう保全を図る。 | 一切の建築行為の禁止。ただし、自然環境の保全又は町の振興を図るため特に町長が許可したものについてはこの限りではない。 |
別表第3(第16条関係)
届出に必要な関係書類
図面の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項及び内容 |
(1) 計画趣旨説明書 | | 設計の方針 |
(2) 美の基準調書 | | |
(3) 建設行為計画書 | | 建設行為の計画を詳細に記入 |
(4) 関係法令調書 | | |
(5) 位置図 | 10,000分の1以上 | 事業区域を明示 |
(6) 案内図 | | 住宅地図の写しに事業区域を明示 |
(7) 公図写し | | 所轄法務局備付けのものの写しに事業区域を明示 |
(8) 現況図 | 500分の1以上 | 地形、区域の境界、近隣の状況、地盤高、植生現況、分布現況等、計画地のありのままの姿を明示 |
(9) 土地利用計画図 | 500分の1以上 | 公共公益施設(公園、緑地、駐車施設、消防施設、道路、上水道施設、排水施設、環境衛生施設、下水道施設、その他の公共公益施設)の位置及び形状、予定建築物等の位置並びにその面積表を明示 |
(10) 建築物等の立面図及び各階平面図 | 250分の1以上 | 立断面図には、近隣の地形・平均地盤面を記入し、高さの算定方法を詳細に記入 |
(11) 緑地計算表 | | |
(12) 現況写真 | | 事業区域の現況が把握できるよう、可能な限り多くの方向、角度から撮影 |
(13) その他町長が必要と認めた書類 | | |
別表第4(第18条関係)
申請に必要な関係書類
図面の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項及び内容 |
(1) 建設行為計画書 | | 建設行為の計画を詳細に記入 |
(2) 関係法令調書 | | |
(3) 美の基準調書 | | |
(4) 説明会等実施状況報告書 | | 説明会等の開催日、参加人、協議内容等を詳細に記入 |
(5) 位置図 | 10,000分の1以上 | 事業区域を明示 |
(6) 案内図 | | 住宅地図の写しに事業区域を明示 |
(7) 公図写し | | 所轄法務局備付けのものの写しに事業区域を明示 |
(8) 現況図 | 500分の1以上 | 地形、区域の境界、近隣の状況、地盤高、植生状況等を明示 |
(9) 実測図 | 500分の1以上 | |
(10) 土地利用計画図 | 500分の1以上 | 公共公益施設(公園、緑地、駐車施設、消防施設、道路、上水道施設、排水施設、環境衛生施設、下水道施設、その他の公共公益施設)の位置及び形状、予定建築物等の位置並びにその面積表を明示 |
(11) 公共公益施設の断面図及び構造図 | 100分の1以上 | |
(施設の構造等が明確となる縮尺) | |
(12) 造成計画平面図及び断面図 | 500分の1以上 | 断面図については、高低差の著しい箇所について作成すること |
(13) 擁壁等の構造図 | 50分の1以上 | |
(14) 建築物の立面図、各階平面図及び立断面図 | 250分の1以上 | 立断面図には、近隣の地形・平均地盤面を記入し、高さの算定方法を詳細に記入 |
(15) 日影図 | 500分の1以上 | |
(16) 緑地計算表 | | |
(17) 水使用量計算書 | | |
(18) 雨汚水流量計算書 | | |
(19) その他町長が必要と認めた図書 | | |
 第1号様式
第1号様式(第16条関係)
 第2号様式
第2号様式(第17条関係)
 第3号様式
第3号様式(第18条関係)
 第4号様式
第4号様式(第19条関係)
 第5号様式
第5号様式(第19条関係)
別図 省略